「○○ちゃん」と、親しみを込めて名前に“ちゃん付け”される――職場や飲み会の席ではよくある光景です。軽い気持ちで「親しみで呼んでるだけ」と言う人も多いでしょう。しかし、近年「ちゃん付け やめて ハラスメント 裁判」というキーワードで検索されることが増えています。つまり「その呼び方って、本当に大丈夫なの?」という疑問を持つ人が急増しているのです。
2025年10月23日、東京地方裁判所で判決が言い渡され、「○○ちゃん」と名前を“ちゃん付け”で呼ばれ、さらに「体形いいよね」「かわいいね」と言われた職場の女性が、年上同僚男性に対して賠償を求めた訴訟において、「許容される限度を超えた違法なハラスメント」として 22万円 の支払いを命じられました。
この判例はまさに、「呼び方ひとつ」がハラスメントとして訴えられる時代に入っていることを示しています。本記事では、呼び方がハラスメントとされる背景、今回の具体的な裁判例の詳細、そして「ちゃん付け やめて」を実現するための現実的な対策まで、丁寧に解説していきます。

言葉が出ない・・・。
呼び方がハラスメントに?「ちゃん付け やめて ハラスメント裁判」の背景
「ちゃん付け」とは何か
日本語において「〜ちゃん」という敬称(あるいは親称)は、主に幼児、子ども、家族内、極めて親しい間柄、または親しみを込めて使う呼び方です。社会人同士の職場で成人が使われる場合、それが「可愛がり」や「軽く扱われている」ニュアンスを含むことがあります。
職場において、年齢・役職・性別が異なる相手に対して「○○ちゃん」と呼ぶと、「尊重されていない」「大人として認めてもらえていない」と感じる人が少なくありません。こうした背景があるため、「ちゃん付け」が単なる愛称・あだ名として捉えられず、ハラスメントの文脈で問題になりつつあります。
なぜ今「ちゃん付け」が問題視されるのか
ハラスメントに対する意識の変化
近年、日本社会では職場におけるハラスメント(セクハラ・パワハラ・マタハラなど)の意識が高まっており、言葉遣いや呼称も対象になっています。たとえば、受け手が「不快」と感じる言葉を発した側に悪意がなくとも、就業環境を害する行為として評価されるケースがあります。
法的・裁判実務の進展
今回のように「ちゃん付け やめて ハラスメント 裁判」という言葉が注目されるようになった背景には、呼称・あだ名だけでも「違法なハラスメント」と判断された裁判例の存在が影響しています。実際、複数のメディアが「○○ちゃん呼びはセクハラ認定」という見出しで報じています。
職場の多様化と価値観変化
ジェンダーや年齢、多様な働き方の進展に伴い、従来の「親しみの文化」「先輩後輩文化」がそのまま通用しない職場も増えています。そのなかで「ちゃん付け」が受け手にとって“居心地の悪い”呼び方だったという意識が広まり、「なんとなく許容していた呼称」が見直されつつあるのです。

意識的には気を付けているけど・・・。ねぇ~。
最新判例:ちゃん付けで裁判に至ったケース
事件の概要
2025年10月23日、東京都内の営業所を有する大手物流会社である 佐川急便 の営業所に勤務していた40代の女性が、年上の元同僚男性から以下のような扱いを受けたと主張しました。
- 「○○ちゃん」と氏名を“ちゃん付け”で呼ばれた
- 「かわいい」「体形良いよね」といった外見・体形に関する発言をされた
- その後、うつ病と診断され退職に至った
女性は男性とともに、会社(佐川急便)にも使用者責任を問い、慰謝料として約550万円を請求しました。
裁判所の判断
東京地裁は、被告男性に対して女性側への賠償金22万円を支払うよう命じ、「許容される限度を超えた違法なハラスメント」と認定しました。判決文では次のような指摘があります(要旨整理):
- 「ちゃん付け」は幼児・子どもに向けた呼称であり、成人同士の職場関係において業務上必要性は見いだしがたい」
- 被告男性の「○○ちゃん」と呼んだ言動及び「体形良いよね」「かわいいね」という発言が、女性の羞恥心・劣等感を生じさせ、精神的苦痛を与えたと認められた。
- 被害女性がうつ病と診断され、退職に至った因果関係については、呼称・発言が直接原因とまでは認められなかったものの、「業務において安定した就労環境が損なわれた」との観点から使用者責任も問題とされた。
- また、会社(佐川急便)は別途、女性側と和解金70万円を支払う内容で和解しており、企業としての安全配慮義務・環境整備の必要性も示唆されました。
判例が示すメッセージ
この裁判から得られる重要な教訓を整理します。
- 呼び方ひとつでも、受け手が「不快」「子ども扱いされた」と感じれば、ハラスメントとして法的に問題となる可能性があるということ。
- 「ちゃん付け」呼びだけが問題なのではなく、そこに外見や体形への発言、継続的な言動、就労環境への影響など複数の要素が重なって評価されているという点。
- 企業・使用者が被害を把握していたか、対応していたかどうかも、使用者責任の判断において重要なポイントとなる。
- これまで「軽いあだ名」「親しみの証」として捉えられていた文化が、受け手の視点から見直される段階に入っているという社会潮流が、法的実務にも反映されてきています。

体形はダメでしょ。
“ちゃん付け”がハラスメントとされる典型的なパターン
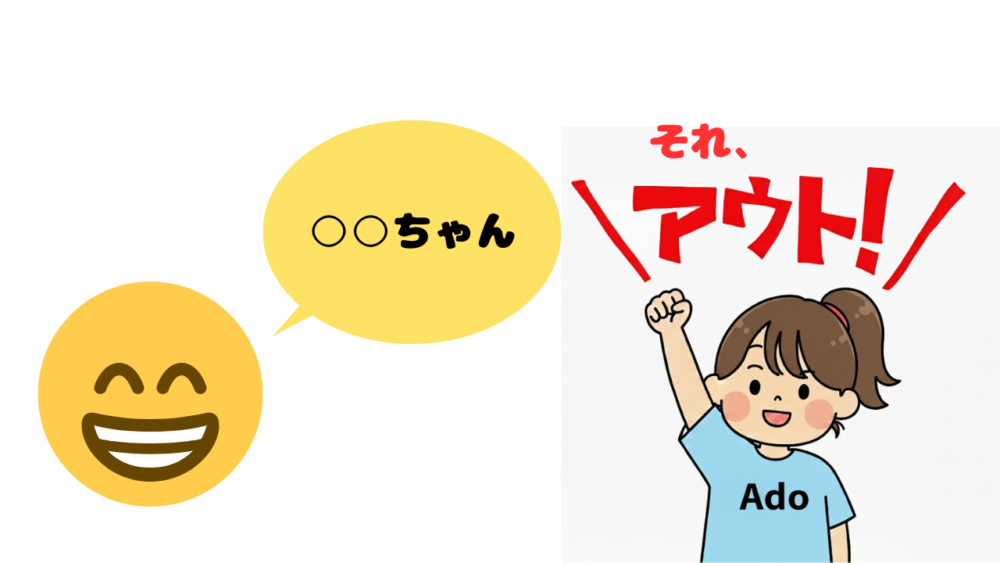
セクハラ的側面
“ちゃん付け”がセクハラ(性的ハラスメント)として扱われる場合、次のような条件がしばしば見られます。
- 呼び方が「未熟・幼児化された扱い」を想起させる。
- 呼びかけとともに、外見や体形、服装など身体的・性的なニュアンスのある発言がある。「かわいいね」「体形いいよね」など。
- 受け手がその呼び方・発言により、不快感・羞恥心・心理的苦痛を感じている。
- その言動が一度きりではなく継続しており、職場の雰囲気・働き方に影響を及ぼしている。
パワハラ的側面
一方、“ちゃん付け”がパワハラ(パワーハラスメント)として位置づけられる場合もあります。典型的には:
- 年上・上司・先輩が部下に対して「○○ちゃん」と呼び、役職差・年齢差を背景に用いる。
- 呼称が「子ども扱い」「未熟扱い」と受け取られ、評価・昇進・学びの機会などに影響を及ぼす可能性あり。
- 受け手が「大人として扱ってもらえない」「尊重されていない」と感じることで、職場環境が悪化する。
判断ポイント
「ちゃん付け やめて ハラスメント 裁判」に関して抑えておきたい判断ポイントは以下です。
- 呼称が業務上必要だったかどうか。本件では「業務上用いる必要性はない」と裁判所が指摘しました。
- 呼称だけでなく、その前後の言動・態度・職場環境がどうか。
- 受け手が「不快・苦痛」を感じ、就業環境(休職・退職・精神的病気など)に影響を受けているか。
- 企業・上司の事前・事後対応があったか。相談窓口・職場研修・是正措置といった施策。
- 他のハラスメント(外見・体形・性別発言など)と連動していないか。
“ちゃん付け”呼びをやめる/伝えるための現実的なステップ
個人としてできること
職場で「○○ちゃん」と呼ばれて居心地が悪い、あるいは自分が呼びかける側で無意識かも、という時にできる対策を整理します。
- 自分の気持ちを整理する
– 呼ばれて「なんだかモヤっとする」「子ども扱いされた気がする」と感じるなら、その違和感をまず自分で整理しましょう。
– その呼び方がどのような文脈で使われているか(業務指示時/雑談時/他の社員の前)を振り返ってみましょう。 - やんわり伝える
– 上司・同僚に対して、「すみません、○○さんと呼んでくれたほうが気持ち的に楽です」とお願いしてみる。
– 「ちゃん付けで呼ばれると、ちょっと“子ども扱い”されてる気がしてしまって…」など、自分の感じたことを伝えるのも効果的です。
– 角を立てず、相手の善意を否定しないスタンスで伝えることがポイントです。 - 記録を取る
– 呼ばれた日時・場所・状況・誰に・どんな言葉で・どのように感じたかをメモしておきましょう。
– 発言が続いていた/相談したけれど改善されなかった/体調を崩したなどの場合、後々ハラスメントとして主張しやすくなります。 - 相談窓口を活用する
– 職場にハラスメント相談窓口があるなら、早めに相談を検討しましょう。
– 「ちゃん付け やめて ハラスメント 裁判」という言葉で検索している人は、既に「自分のケースは許されるのか?」を真剣に考えている段階です。早期の相談が重要です。 - 必要なら専門機関に相談
– 産業医・労働基準監督署・弁護士など、必要に応じて専門家に相談することも選択肢です。特に精神的な影響(うつ病・休職・退職)が出ている場合は、証拠を整える意味でも専門家の支援が有効です。
企業・管理職としてすべきこと
企業や管理職として、「呼び方」「あだ名」「ニックネーム」といった文化も、ハラスメント防止の観点から整備すべきです。
- 就業規則・ハラスメント方針の明確化:呼び方・あだ名・ニックネームに関してガイドラインを作り、「尊重ある呼び方」「業務上必要のない軽い呼称の回避」などを定める。
- 研修の実施:言葉遣いや呼称もハラスメントにつながり得ることを従業員に伝える。特に最新の裁判例(今回の「ちゃん付け」呼びも)を紹介し、「軽い冗談」がハラスメントになり得ることを示す。
- 相談窓口・報告体制の整備:呼称・ニックネームに関して違和感や不快感を抱きやすいのは若年層・女性・パート・異動直後の社員など。相談しやすい環境を整える。
- 早期対応と記録:違和感を訴えられた場合には迅速に対応し、記録を残す。これは使用者としての安全配慮義務を果たすことにもつながります。今回の判例でも、会社側が和解金70万円を支払ったという報道があります。

この判例で、また研修が増えるなぁ~。
ちゃん付け やめて ハラスメント 裁判で覚えておきたい5つのポイント
- 呼称だけが問題ではない
“ちゃん付け”という呼び方だけで自動的にハラスメントとされるわけではありません。呼称の背景、継続的な発言、業務上の必要性の有無、受け手の感じ方などが総合的に判断されます。 - 業務上の必要性があるかどうか
判例では「業務で“○○ちゃん”と呼ぶ必要性は見られない」と判断されました。 - 受け手の立場・感じ方が重要
受け手が「子ども扱いされた」「軽く見られた」と感じたかどうかが、ハラスメント判断の鍵です。 - 企業・上司による対応が問われる
相談窓口・是正措置・職場環境整備など、使用者としての義務を果たしていたかが評価されます。 - 他の要素(外見・体形・性別発言)との関連にも注意
呼び方に加え、体形・容姿・性別に関する発言があった場合、セクハラ・差別的発言としての評価が高まります。今回の判例では「体形良いよね」との発言が判断材料となっています。
“ちゃん付け”が許容されるかどうかを見分けるチェックリスト
以下のチェックリストを使って、ご自身の職場環境や言われ方を振り返ってみましょう。
- ○○ちゃんと呼ばれて、自分はどう感じたか?(子ども扱い/親しい/なんとも思わない)
- 「ちゃん付け」で呼ばれることが頻繁か、状況的に限定的か。
- その呼び方に業務上の必要性があるか?(指示・報告・チーム内コミュニケーション)
- その呼び方とともに、外見・体形・容姿・性別に関する発言があったか?
- 呼び方によって、心理的・業務的影響があったか?(モチベーション低下/休職/退職)
- 相談できる窓口・対応体制が職場にあるか?上司・人事に訴えやすいか?
このチェックリストで「はい」が多ければ、多めの注意や改善を検討する価値があります。
まとめ
「ちゃん付け やめて ハラスメント 裁判」というキーワードが示すように、かつて「軽い親しみ」として使われていた呼び方が、今や法的な観点からも見直される時代になりました。今回の判例(2025年10月23日付、東京地裁)では、40代女性が「○○ちゃん」と呼ばれ、「体形良いよね」「かわいいね」と言われ続けたことを巡り、「許容される限度を超えた違法なハラスメント」として賠償命令が下されました。
もし、あなたが職場で「○○ちゃん」と呼ばれて居心地の悪さを感じていたり、自分が“ちゃん付け”で呼んでしまっていることに違和感を抱えていたりするなら、それは侮ることのできないサインです。呼び方はたった一言ですが、そこに含まれる意図・関係性・継続性・受け手の感じ方が、ハラスメント評価に直結する時代です。
職場において親しみを持って呼び合う文化を保つことは決して悪いことではありません。ただし、**「相手がどう感じるか」**という視点を持つことが、安心して働ける環境づくりの第一歩です。もし違和感があるなら、今日から少しだけ呼び方を見直してみませんか?その小さな一歩が、職場の風通しをぐっと良くするきっかけになるかもしれません。

日本もアメリカのように、訴訟の国になりつつあるなぁ~。
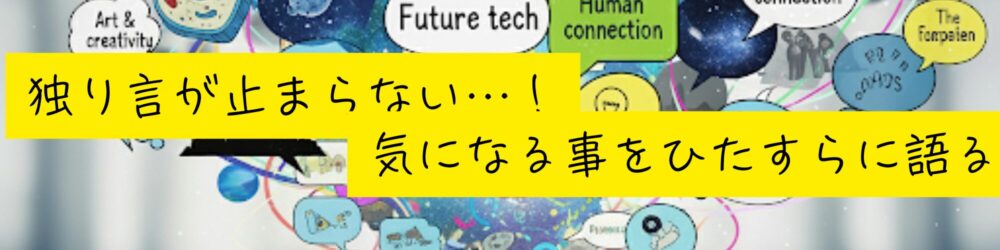
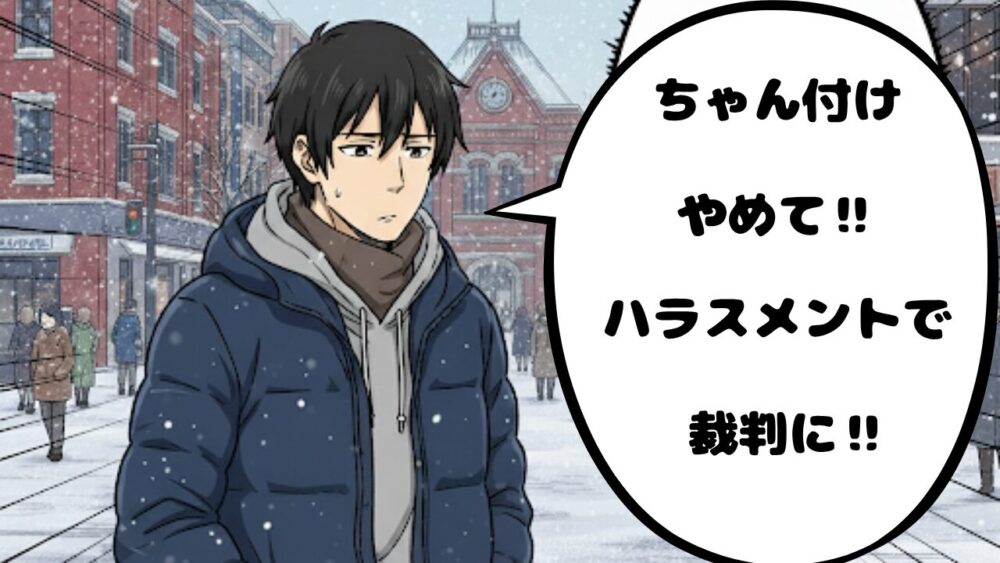


コメント