夜なのに頭の中で音楽が繰り返して眠れない…それ、イヤーワーム(ディラン効果)です。
とくにADHD傾向のある人は、この現象に悩まされることが多く、なかなか寝付けずイライラする人も少なくありません。
最近の2025年以降の最新研究によれば、この眠れないイヤーワームの原因のひとつは、まさに脳の仕組みにあることがわかってきました。
今回はその「なぜ?」「どう対策?」に迫ります。
ADHDと眠れない関係の裏側:脳のリズム・メラトニン・反応性のせい?
ADHDと不眠の負のループ
2025年7月のサウサンプトン大学の研究では、ADHD傾向が強い人ほど不眠症が重くなり、結果として生活満足度が下がる「負のループ」が働くことが示されました。
不眠で集中力や感情のコントロールがやられ、ADHD症状がさらに悪化しやすくなるんですね 。
メラトニンの分泌が遅いADHD
さらに、2025年2月の浜松大学らによる研究では、ADHDの子どもでは「眠る準備を告げるホルモン=メラトニン」の分泌が遺伝的に遅い傾向があることも明らかに。
つまり「寝なきゃ」と思っても体が自然に眠る準備を始めてくれないんです。

次の日に重要なことがあるときほど、こういう状況になりますね。
ストレスで爆発的に眠れなくなる「睡眠反応性」の高さ
2024年の研究では、ADHDの大人はストレスへの反応から不眠になりやすい「高い睡眠反応性」が原因として注目されました。
これは、ちょっとしたストレスや生活リズムの変化だけでも眠れなくなりやすい特性です。
イヤーワームが止まらないのは、脳の“勝手なメロディー記憶”のせい
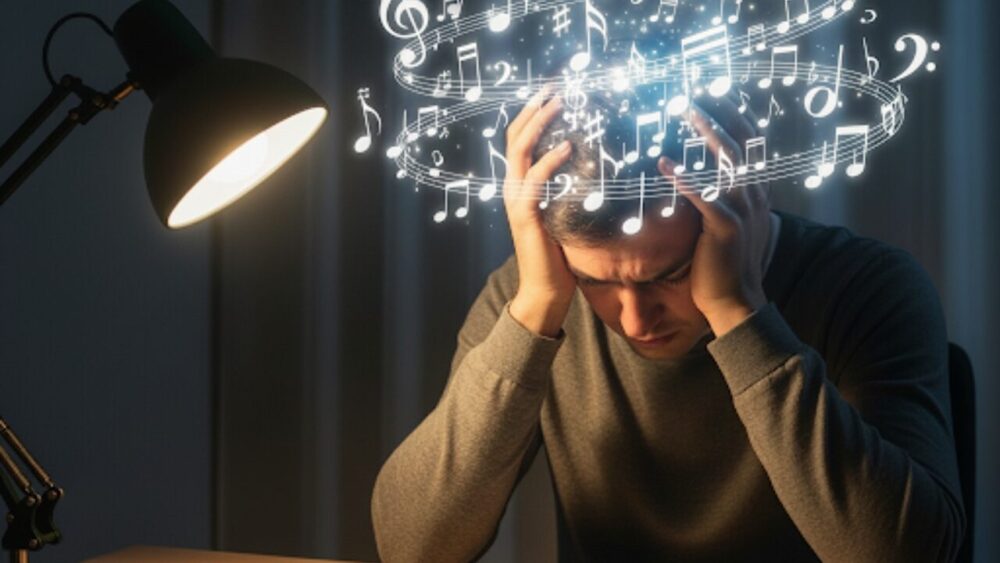
イヤーワームとは、音楽のフレーズが脳内でループする現象。
科学的には「短期記憶のサブボーカル反復」が止まらないせい、と説明されます。
ADHDの人は「脳の多動」や「自動思考」が活発なため、イヤーワームが起こりやすく、さらにストレスや疲労で止められず眠れないことも。
結果として、「もう眠らなきゃ!」と思えば思うほどメロディーが頭に張り付いてしまうんです。
具体的な対策:眠れないイヤーワームをぶっ飛ばす方法
● ガムを噛む or 脳トレに集中
研究でも効果があるとされる方法が、ガムを噛むことでサブボーカルを妨害する方法や、アナグラムなど脳を使う別タスクに集中すること。
● “キュアソング”でループ脱出
ループしているメロディーとは別の置き換え曲(キュアソング)を聞いたり、ループしている曲を最初から最後まで通して聞いたりすると、脳内の再生モードがリセットされます。
● 睡眠環境の“質”を見直す
ADHDの人にとっては、ただ寝る時間を増やせばいいわけじゃない。
「深い眠り(=スロウウェーブ睡眠)」が取れているかが大事。
寝る時間を一定にし、ベッドでの時間を限定する「スリープコンソリデーション」も効果的。
● 睡眠反応性が高い人向けの対処
不眠の深刻さはストレスへの反応性に左右されるので、認知行動療法 for 不眠(CBT-I)や睡眠制限療法が効果的ですが、ADHDの人にはアクセスが難しい場合も多いため、早い段階で簡易的なセルフケアを試すのも大事。
● 専門医への相談も選択肢に
特にイヤーワームが強迫的に続いて日常に支障がある場合、「強迫性障害」や「受験うつ」などの可能性もあるため、専門クリニックでの相談も検討しましょう。

頭の中で音楽が繰り返しているだけなのに・・・。怖いですね。
どうしてこの問題が起きちゃうのか?ADHDの脳の特徴を押さえておこう
ADHDの脳は、前頭前野や線条体、自律リズムに関わる神経経路(ドーパミン・ノルアドレナリン系)の機能が弱い傾向があります。
- そこが弱いと自己調整(時間管理、感情制御、集中)が苦手に。
- メラトニン分泌や深い睡眠への導入もスムーズに行われず、不眠や頭の中のモヤモヤ(=イヤーワーム)が止まりにくくなります。
さらに、ストレス反応が強く、回復も弱いという特性があるため、ちょっとした緊張や生活のズレが眠りの質をガクンと下げてしまいます。
まとめ:イヤーワーム ADHD 対策 眠れないその原因は、脳の仕組みにあった!
- ADHDの人は、メラトニン分泌の遅れ・高い睡眠反応性・脳の多動構造により、「眠れないイヤーワーム」が起きやすい。
- 不眠とADHD症状は悪循環を生み、生活の質を下げてしまう。
- ガムを噛む/脳トレをする/キュアソング/睡眠環境整備/セルフCognitive Behavior療法など、手軽に取り組める対策がある。
- 深刻な場合は専門医への相談も検討しつつ、自分の生活リズムと脳の特性に合った対応を始めてみてください。

「脳の仕組み」のせいなら、原因が明確で自分への言い訳にもなるし(笑)、対策もしやすいですよね。
一歩ずつ、夜のイヤーワームをうまくかわして、心地よい夜を取り戻しましょう。
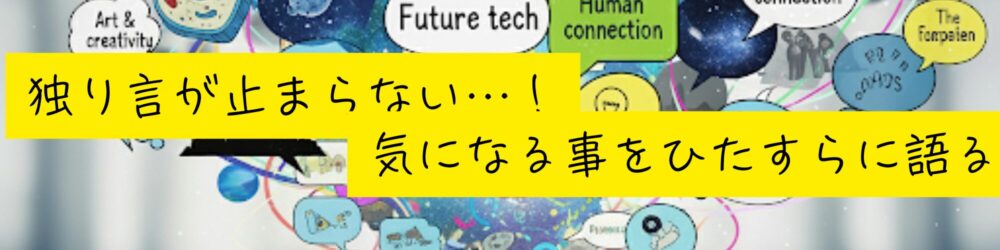
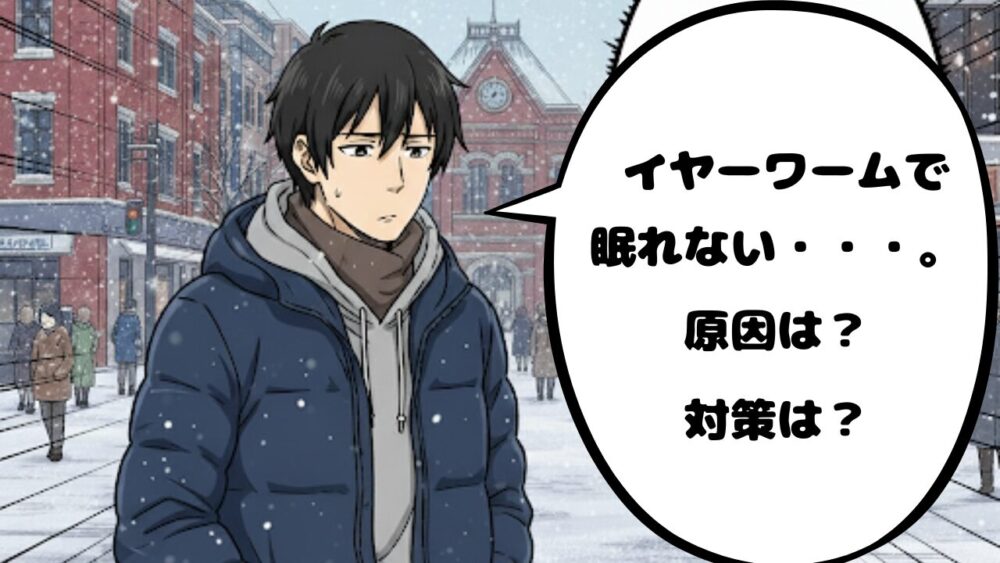


コメント