冬が近づくにつれて、「今年はインフルエンザ予防接種を受けたほうがいいのかな?」と迷っている人、多いのではないでしょうか。中でも「インフルエンザ予防接種 しないとどうなる? 症状 比較」というキーワードで検索しているあなたは、「接種をしなかったら、どんな症状が出るのか?」「打った人と比べてどれくらい違うのか?」という疑問を抱えているはずです。
この記事では、最新データ(2025年以降)をもとに、接種しなかった場合の可能性、接種者との症状差、さらに自分や家族にとっての判断材料を整理してお伝えします。家族の健康も気になる30〜50代の方、職場で多くの人と接する20〜30代の方、高齢のご両親を持つ方、ぜひ参考にしてください。
インフルエンザ予防接種 しないとどうなる? 基礎知識を押さえよう
インフルエンザとはどんな病気?
まず、「インフルエンザ」がどういうものかをざっと確認しておきましょう。インフルエンザウイルスが鼻・喉・眼の粘膜から体内に入り、細胞内で増殖して発症します。咳・喉の痛み・鼻水という風邪っぽい症状から始まり、急に38〜40℃の高熱、頭痛、筋肉・関節の痛み、全身倦怠感が出るのが典型的です。
特に高齢者・乳幼児・持病のある人では「肺炎」「脳症」「入院」「死亡」など重症化・合併症のリスクが高いことも指摘されています。
接種しないと起こり得ること
「インフルエンザ予防接種 しないとどうなる? 症状 比較」という観点で見ると、接種しない場合の主なポイントは次の通りです:
- 発症率が高くなる:ワクチンを打たない人は感染・発病する確率が、接種者より高めになります。
- 症状が重く・長く出る可能性:発熱や全身倦怠感、咳・鼻水が強く出る、回復まで時間がかかるというケースが増えがちです。
- 合併症リスクが上がる:特に「肺炎」「脳症」「呼吸困難」など、重症化に至る可能性が高まります。
- 社会的・家庭的コスト増:病院受診・入院・仕事や学校の欠席・家庭内感染など、個人だけではなく周囲にも影響が出ることがあります。
つまり、接種を見送る=“安心できる”とは言えず、一定の「リスクを抱える可能性」があるということをまず理解しておきましょう。
接種した人と打たなかった人の症状比較 ~どれくらい差が出る?
「比較」が最も知りたいポイントですね。以下で具体的なデータとともに見ていきます。
発症リスクの差
国内データでは、例えば65歳以上の高齢者福祉施設入所者を対象にした研究で、「ワクチン接種群では発病を34~55%阻止」「死亡を82%阻止」という報告があります。
また、健康な成人では、接種による発病リスクの減少が約50〜60%という報告も出ています。
つまり、打った人でも100%かからないわけではないですが、「打たない人に比べて明らかにリスクは下がる」ということになります。
症状の重さ・回復時間の差
発症したとき、打った人と打たなかった人ではどう違うかというと:
- 接種した人:発熱や倦怠感の程度が軽め、回復が比較的早い傾向にあるという報告あり。
- 接種しなかった人:発症したら、症状が強く出る・合併症に進む可能性が上がる。高齢者や疾患持ちでは「入院」「死亡」に至るケースも多く、打った人との差がより際立ちます。
合併症・重症化の差
「インフルエンザ予防接種 しないとどうなる? 症状 比較」で特に押さえておきたいのは、合併症の差です。
- 高齢者や持病がある方が、ワクチン未接種の場合、肺炎・脳症・心筋梗塞・脳卒中などのリスクがかなり上がるという報告あり。
- 接種者ではこうした重症化・入院・死亡リスクがかなり下がる傾向あり(例:65歳以上で死亡阻止効果約82%)
症状比較表(打つ人 vs 打たない人)
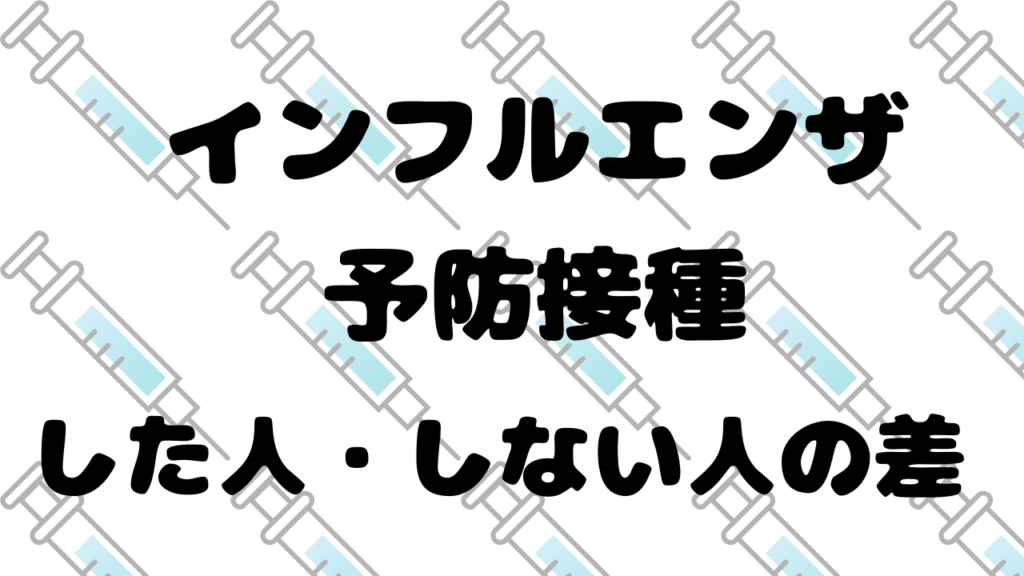
以下に分かりやすく比較表を作成します。
| 項目 | 接種した人の場合 | 接種しなかった人の場合 |
|---|---|---|
| 発症率 | 約30〜60%減少(年齢による) | 基準リスク(高齢・幼児・持病ありでさらに上昇) |
| 発熱・倦怠感・筋肉痛の程度 | 比較的軽め・回復が早めという傾向あり | 症状が重め・回復に時間がかかる傾向あり |
| 合併症(肺炎・脳症など) | リスク低減(入院・死亡リスクも下がる) | リスク上昇、特に高齢者・持病ありでは重大化の可能性大 |
| 入院・死亡リスク | 高齢者施設で死亡82%阻止の報告あり | その逆:未接種でリスク高め |
| 家族・社会への影響 | 感染源になりにくい・欠勤・休校リスク低 | 感染源になりやすい・欠勤・休校・家庭内感染リスク高 |
| 補助・安心感 | 接種しておくことで安心感・次の感染リスク低 | 打たない選択なら“リスクを受け入れる”覚悟が必要 |
この表を見ると、「打たないことで得られるメリット(費用・時間節約など)はあるかもしれませんが、打つことで得られる“安心・リスク低減”の利点がかなり明確に見えてきます。
どんな人が特に「打たないとどうなる?」リスクが高いの?
年齢・置かれた状況別リスク
「インフルエンザ予防接種 しないとどうなる? 症状 比較」を考えるとき、特に注意しておきたい人がいます。
- 65歳以上の高齢者:免疫力低下・体力低下と重なり、インフルエンザにかかると重症化・合併症のリスクが非常に上がります。
- 6か月以上5歳未満の小児:体の防御機能が未完成で、合併症の可能性も高めです。
- 持病がある人(心臓/腎臓/呼吸器など):基礎疾患があると、インフルエンザにかかった際の被害が大きくなりがちです。
- 妊婦・免疫機能の低下した人:ウイルス感染・重症化リスクが高く、周りに影響を与えやすい立場です。
- 乳幼児・高齢者と同居/多くの人と接する職業(介護・教育・医療・接客):感染を媒介する可能性があるため、打たない選択には“自分だけでなく周囲”まで考慮が必要です。
家族・社会への影響も視野に
また、「自分は大丈夫」というケースであっても、接種しなかったことで起こる“家族・社会への影響”を忘れてはいけません。例えば:
- 家族に乳幼児・高齢者・持病のある人がいる →「自分が感染源になったら?」という不安
- 職場・学校で流行が起きると、休み・欠勤・周囲への影響が出る
- 医療費・入院・長期療養が必要になると、時間・金銭・心理的負担が増える
つまり、接種・非接種の選択は“個人の話”だけでなく“家族・社会の話”として考えるべきです。
「打たない選択」をする際の注意点と考え方
打たない=リスクゼロではないという現実
もし「今年は打たない」「私は健康だから大丈夫」と考えているなら、以下のことは認識しておきたいです。
- ワクチンを打っても100%かからないわけではないですが、打たない場合はリスクがかなり高めということ。
- 流行株・接種のタイミング・体調・免疫力など、条件によって状況は大きく変わるため、「去年は大丈夫だったから今年も」という安心材料だけでは不十分です。
- もし発症したら、「入院・長期療養・家庭内感染・職場欠勤」など“打たなかったコスト”が出る可能性があります。
打たなかった人がやるべき補完策
接種を見送るなら、下記のような補完的な対策をきちんと行うことが大事です。
- 手洗い・うがい・咳エチケット・マスク・換気の徹底
- 混雑・密な場所を避ける、流行期に人と多く接触する機会を減らす
- 栄養・睡眠・ストレス対策など、体調管理を普段以上に強化
- 家族や周囲に高齢者・小児・持病ありの人がいるなら、接触機会の配慮・マスク着用などを徹底
- 兆候が出たら速やかに医療機関に相談&早期治療を想定
とはいえ、これらの対策だけで“打った人と同等”にはなりません。リスクを受け入れた上での補強策、という位置づけで考えるのがベストです。
接種した方が安心な理由と「インフルエンザ予防接種 しないとどうなる? 症状 比較」で見えてくるメリット
接種で得られる主なメリット
接種することで以下のような利点が確認されています:
- 発症そのものをある程度抑えられる(成人で発病予防効果約40〜60%、小児で60%前後)
- 発症しても、症状の重さを軽減し、入院・死亡・合併症のリスクを下げられる
- 家族や周囲への感染拡大を防ぐ可能性が上がる=“自分が守る側”として安心感が得られる
- 流行期に「発症・療養・休職・欠席」といったコストを下げることができる
「打たないとどうなる?」を考えると…
この比較から浮かび上がるのは、接種しない選択をすると次のような不安が出てくるということです:
- 発症率が上がる → 症状が重めになる可能性がある
- 合併症・入院・死亡のリスクが上がる → 特に高齢者・持病ありの場合
- 家族・社会・職場に対する影響が出やすい →欠勤・家庭内伝染・医療費増
- その分、時間・お金・心理的な負担が増える可能性あり
こうしたことから、「接種をしておく価値」がかなり明確に見えてきます。
接種時期・ワクチンのタイプ・2025年の最新情報
接種時期の目安
日本では例年、12月〜4月に流行があり、ピークは1〜3月あたりのケースが多いです。
接種後、一般には2週間ほどで抗体が上がり、3〜4カ月後から効果が徐々に低下するという報告もあります。
したがって、10月〜12月上旬には接種を終えておくのが理想とされます。
2025/26シーズンのワクチンに関するポイント
- 国内では2025/26シーズンから、ワクチン株が改良され、4価ワクチン(A型2型+B型2株)への移行が進んでいます。
- 特に高齢者向けに「高用量ワクチン」が開発されており、通常ワクチンよりも予防効果が高められているという報告があります。例えば「高用量ワクチンで標準用量ワクチンに比べ発症率低下24.2%」という臨床試験データも。
ワクチンの効果と限界を理解しておく
- 接種しても100%発症を防げるわけではありません。特にウイルス株の一致率や個人の免疫力により“どれだけ効果が出るか”は変わります。
- ただし、ワクチンの最も大きな役割は「重症化予防」であると、厚生労働省が明言しています。
- また、接種後も「手洗い」「マスク」「換気」など基本的な感染予防を継続することで、さらに安心度が高まります。
実際にどう判断・行動すべきか?
あなた・ご家族の状況を整理してみましょう
「インフルエンザ予防接種 しないとどうなる? 症状 比較」で得た情報をもとに、次のように考えてみると判断がしやすくなります:
- 家族構成:乳幼児・高齢者・持病のある人がいるか? → いるなら接種優先度高
- 自分自身の健康状態:持病なし/あり、体力・免疫の状態など
- 接触環境:職場・学校・施設で多くの人と接しているか? →多ければ接種価値上
- 流行状況:地域・今シーズンの流行の始まり状況・ワクチン株の一致率など
- 接種による安心感と、打たなかった場合のリスク・コスト(時間・お金・安心)を比較
“打たない”選択をするなら
もし接種を見送る選択をするなら、次のようなことを準備・実行しておくと安心です:
- 流行のピークを理解して、密な場・人の集まる場所を避ける
- 基本的な感染予防をいつも以上に丁寧に行う
- 体調管理を普段以上に意識(睡眠・栄養・運動・ストレス)
- 発症した際の対策を家族・職場と共有しておく(早期受診など)
- 自分だけでなく、「もし自分が感染源になったら?」という視点も持つ
“接種”をおすすめするケース
以下の条件に当てはまるなら、接種をおすすめします:
- 高齢者・子ども・持病のある家族がいる
- 職場・学校・施設など多数の人と接する環境にある
- 流行期に入っていたり、地域で感染拡大の兆候がある
- 自分自身が重症化リスク(免疫低下・慢性疾患)を自覚している
まとめ
「インフルエンザ予防接種 しないとどうなる? 症状 比較」という視点から見ると、接種をしなかった場合には“リスクの上昇”が明らかです。発症そのものを防ぐ確率が低くなり、症状が重く出る、回復に時間がかかる、合併症・入院・死亡の可能性が上がる…こうした傾向がデータから見えています。そして、接種した人との差—発症率・症状の重さ・合併症への展開—を比較すると、「接種をしておく価値」がかなり明らかです。
もちろん、接種だけですべてが安心というわけではありません。打った後も、手洗い・うがい・マスク・換気・体調管理といった基本的対策を継続することが重要です。また、打たない選択をするなら、その分だけ“リスクを受け入れる覚悟”と“補完策を実行する覚悟”が必要です。

今年も冬が近づいており、インフルエンザの流行期がやってきます。少しでも安心して過ごせるよう、この記事をきっかけに「自分・家族にとっての判断」を改めて考えてみてください。「打たないとどうなる?」を知ったうえで、納得できる選択をして、健康な冬を迎えましょう。
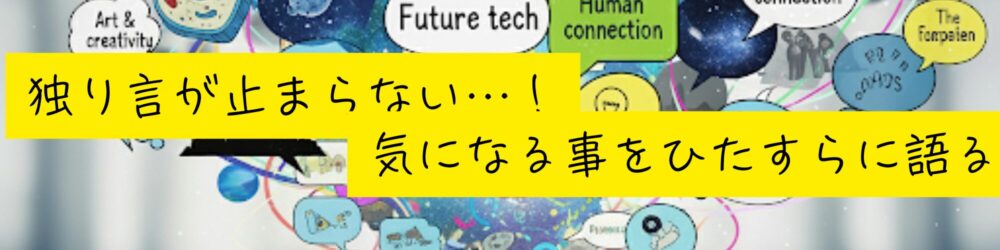
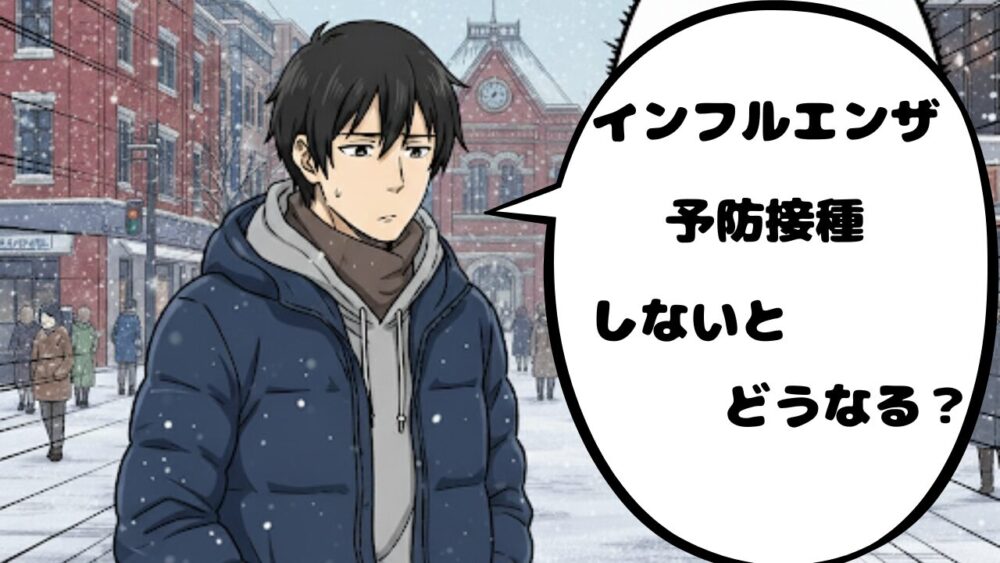
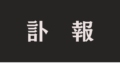

コメント