「もう戦争だよ」――この言葉が地方の県知事から発せられたとき、多くの人は衝撃を受けたでしょう。特に、自然と共生してきた東北の山あいの暮らしを営む地域では、笑い話や誇張ではなく“本当にそのくらい切迫している”という実感が込められていた言葉です。
今回、その発言の主である佐竹敬久前秋田県知事と、彼が訴えた熊害(=クマ被害)が東北・秋田で “戦時下のような状況” と表現されるに至った背景を、データ・現場証言・制度面から丁寧に振り返ります。
そして、読者であるあなた自身が暮らす地域/山/田畑で「今、何を知り、何を備えるか」もあわせて提案していきます。
「もう戦争だよ」発言の意味と背景
発言の内容と出所
2025年10月23日、ENCOUNT の取材記事で、佐竹前知事が次のように語っています。
「年寄りは散歩ができない。子どもたちは外で遊べない。クマのせいで健康や成長、生活のすべてに影響が出る。こうなると もう戦争だよ、戦争。 普段の日常生活を送れないんだから、戦時下と変わらない」
また、同記事では、実際に「山菜取り・畑・住宅街近く」までクマが出没しており、被害を受けた住民・地域の姿を前知事自身が “知事ではなく住民” として語っています。
加えて、県議会では「お前のところにクマ送るから住所送れ」などの挑発的な発言も出ており、知事という立場から異例の強い語調が注目を集めました。
つまり、この発言は「ただ大げさなキャッチコピー」ではなく、現場で深刻化している被害・住民の恐怖・行政の焦りを象徴する言葉として位置づけられます。
なぜ「戦争」かという比喩
ここで「戦争」という極めて重い言葉を使った理由を整理しましょう。前知事が語るところでは次のような状況が背景にあります:
- 人が人を襲う「クマ」による被害が 人里・住宅近く・通勤路・子どもの遊び場 など、かつて “山の中だけ” だった領域を越えて進行している。
- 被害を受けた住民の身体的・精神的影響が重大で、たとえば「顔をやられる」「目をやられる」「仕事できなくなる」「子どもや老人が外に出られなくなる」という報告があります。
- 地域経済・暮らしの基盤(山菜・果実・観光・散歩・子育て)がクマ被害によって崩れつつある。 >「山菜取りで年に200~300万円稼いで生計を立てているおばあちゃんもたくさんいる。クマが出るから今年は舞茸の出回る量が少ない」
- こうした暮らし・コミュニティ・安全が同時に侵される様子は、戦時下で「日常が奪われ、脅威にさらされる」状況と似ているという認識。
このように、「戦争」という言葉は比喩を超えて、住民の「もう日常ではない」という危機感を表しています。
発言が出たタイミング
発言が出た背景には、以下のような流れがあります。
- 全国的にクマによる人身被害・出没が記録更新ペースで増加。環境省の報告によると、令和5年度は9月以降、10月が特に被害が多かった。
- 秋田県においても「出没・目撃・捕獲数が突出している」と分析されており、2025年も春から“多発”傾向という調査が報じられています。
- 県民・行政双方に対して「これまでの対応では間に合わない」「このままでは生活が壊される」という焦りが積み重なっていた。佐竹前知事は、知事退任直前期にこの問題に強い発信を続けていました。
このようなタイミングで「もう戦争だよ」という言葉が出たことには、危機のピーク感とともに、住民・行政に向けた“目覚めの呼びかけ”的意味合いもあったと考えられます。

今年の目撃回数・襲われたニュースの回数は異常。町中で見るなんてこと滅多になかった。でも、今年は毎日出没してる・・・。
秋田県における熊害の実態:数値と現場から

生息数・出没・人身被害の状況
まず、数値面から整理します。
- 秋田県公式サイトでは、2020年4月時点で県内ツキノワグマの生息数を「2,800~6,000頭(中央値4,400頭)」と推定(カメラトラップ+ベイズ推定)しており、2024~25年に再調査を実施予定としています。
- 環境省の「クマ類による人身被害の発生状況」資料によれば、令和5年度における東北3県(青森・岩手・秋田)での被害が、平成26年度以降で最多を記録し、特に秋田県では「10月」が多く、人家周辺での発生割合が高いというデータが出ています。
- 非公式ながらも、2025年10月21日時点で秋田県内における人身被害が「43件・44名、死亡1名」という報道もあります。
これらを整理すると、“出没数・人身被害数・住民との遭遇確率”のいずれも上昇傾向にあり、数値上からも「もう日常ではない」状況が裏付けられています。
住民・地域で語られる“もう戦争だよ”的実感
数値だけでは伝わりづらいですが、実際に地域の現場では次のような声があります:
- 前知事のインタビューで、知事自身が「うちの目の前でも1人やられたんだ。両目をやられて…むごいもんだよ」 と語っています。
- また、「住宅街から20メートル先のコンビニの前に出たこともあった」というエピソードも示されており、かつては山の奥と思われていたクマが“人の生活圏”近くに出没していることが明らかになっています。
- 山菜取りや果実採取を生計源とする高齢住民にとって、「クマが出るから今年は舞茸の出回り量が少ない」「子どもが外に出られない」という言葉が出ており、地域の暮らし・文化・生計まで被害を受けているという実情が浮かび上がります。
こうした声があるからこそ、知事の「戦争だよ」という表現に住民が違和感を持たない、むしろ“まさにそのくらい切迫している”というリアルが伝わります。
なぜ被害が急増しているのか:原因の整理
なぜここまでクマの被害・出没が増えてきたのか、複数の要因が重なっています。以下では秋田・東北を中心に整理します。
- エサ資源の減少・変動:堅果類(ブナ・ミズナラなど)の結実が不作になる年があり、クマが山の中のエサを得にくくなると人里に下りてくるという傾向があります。
- 人里・里山環境の変化:人口減少・耕作放棄地の増加・林縁部の見通しの悪化などにより、人が少ない里山・藪が増え、クマが人の接近を恐れず活動できる「入りやすい」環境ができています。前知事もこの点を指摘しています。
- 分布域・行動範囲の拡大・移動パターンの変化:クマの分布が拡大し、また活動時間帯・行動範囲が人の活動時間と重なるケースが増えています。山から里へ、人里から住宅近くへという“境界の崩れ”が見えています。
- 情報・通報の増加:出没情報の共有システム(例えば秋田県の「クマダス」)が充実しているため、目撃・遭遇が“可視化”されており、実際の増加に加えて認知の高まりも一因となっている可能性があります。
このような複合的背景によって、被害が“ただ増えている”だけではなく、住民の生活圏に侵入するかたちで増えているという点が重要です。
発言がもたらした波紋と制度的な動き
発言の反響
前知事の発言は、次のような波紋を呼びました。
- 地元住民からは「ようやく言ってくれた」「言葉が重いけど、その通りだ」という声も上がっており、被害と暮らしの危機を代弁したと評価される側面があります。
- 一方、言葉遣いや「クマを送る」といった発言(「お前のところにクマ送るから住所を送れ」)については賛否両論があり、過激さや行政の言葉としての適切性について批判も出ています。
このように、住民の共感と行政としての言葉の重みが交錯した発言だったといえます。
制度・対策の動き
この発言を契機に、あるいはその前から進んでいた制度的な動きも加速しています。例えば:
- 秋田県では「ツキノワグマ等情報マップシステム(クマダス)」を運用し、目撃・出没・被害情報を住民・自治体で共有する仕組みが強化されています。
- 環境省の資料によれば、令和5年度におけるクマ許可捕獲数・出没数が過去最多ペースとなっており、対策強化の必要性が明確になっています。
- 現場対応として、住宅地近く・市街地近くでの出没通報・電気柵・農地の見直し・人家侵入予兆の監視などが自治体・住民レベルで進みつつあります。秋田県公式でも「小屋等侵入は家屋侵入につながるため通報を早めに」という呼びかけがあります。
これらは「言葉だけではない動き」が出ている証左であり、「もう戦争だよ」という言葉に込められた“本気の備え”が制度的にも反映され始めています。
私たちが知っておくべき「戦場化」のサイン
「もう戦争だよ」という言葉を単なる表現に終わらせないために、私たち住民・地域が“戦場化”のサインを知ることが重要です。以下は、実際に秋田県が示している注意点でもあります。
- 小屋・倉庫・空き家へのクマの侵入痕:人家侵入リスクの前段階として、小屋等侵入が増えており、侵入を放置すると家屋侵入につながる。
- 実のなる木・果実・畑・残飯などがクマを誘引する物的条件:特にクリ・カキ・果樹などの管理が不十分な場合、クマが人里に留まる原因となる。
- 通勤・通学路・住宅街近くでのクマ目撃・遭遇:山だけでなく“普通の暮らしの場”にクマが出ているという報告が増えており、「山じゃないから大丈夫」という意識では済まない。前知事の取材で「コンビニの前に出た」という話もありました。
- データ上の「10月ピーク」「人家周辺比率の高さ」:環境省資料によると、9月以降・10月に被害が増える傾向があり、特に人家周辺での発生割合が多いという特徴があります。
これらのサインが重なっている地域・時期では、住民として「日常が侵される」前に備える必要があります。
暮らしを守るために:個人と地域でできること
前知事の言葉を “リアルな警鐘” として受け止め、私たちができる備え・行動を整理します。
個人・家庭レベルでの備え
- 鈴・ラジオ・スマホなど、行動中「音を出す」ことでクマに人の存在を知らせる。秋田県公式もこの点を強調しています。
- 小屋・倉庫・畑の扉や扉の鍵を確実に閉めておく。クマは引き戸やシャッターを開けることもあると注意されています。
- 果実・生ゴミ・飼料などクマが食べるものを放置しない。畑や庭の「見通し確保」「藪刈り」「実のなる木管理」も重要。
- 複数人での山菜取り・散策を心がけ、単独行動を避ける。人家近くや少しでも「出そうだ」という地域では特に慎重に。
- クマとの遭遇時の基本対応を知っておく:「慌てずゆっくり後退」「目を狙われやすいので顔を守る」「撃退スプレー等を携行」など。アウトドア用品研究室でも「人里・市街地でも遭遇事例多い」と指摘されています。
地域・自治体と連携する取り組み
- 出没・目撃情報を地域で共有する:例えば秋田県では「クマダス」マップを住民・自治体で活用。
- 電気柵・果実木の管理・小屋への侵入防止といった物的対策を集落全体で実施。
- 入山禁止区域・危険区域の設定を住民が理解・遵守。秋田県では特に “人が集めた山菜を奪う・人に接近するクマ” が確認された地域では入山禁止措置を取っています。
- 地域防災・野生動物対策の視点から、クマ被害を“個人の問題”ではなく“地域課題”として捉える。前知事も「地域の暮らし・文化・経済が影響を受けている」と訴えていました。

朝のゴミ捨て、意外と怖いんだよねぇ~。
今後の展望:どう変わるべきか

制度・政策の方向性
「もう戦争だよ」という言葉が示すのは“ただの増加”ではなく“人里・暮らしの場で戦っている”という現実です。制度・政策としては以下の方向性が考えられます:
- 生息数管理だけではなく、「人とクマの境界線管理(ゾーニング)」を明確化する。例えば住宅地に近づきやすいクマの行動を分析し、警戒エリアを設定する。
- 山のエサ資源・里山環境の変化を含めた中長期的な「クマ生態⇔人里影響」のモニタリング強化。秋田県でも再推定調査の予定があります。
- 情報インフラ(目撃マップ・通報システム・住民参画モデル)をさらに強化し、被害速報から備えへと住民を動かす仕組み強化。秋田県の「クマダス」はモデルのひとつ。
- 地域住民・企業・行政・研究機関が協働する“クマ被害対策プラットフォーム”の構築。単発の駆除ではなく、共生を含む包括的なアプローチへ。
これらは、「もう戦争だよ」という表現が示す緊急性を制度的に反映する動きと言えます。
住民の暮らしのあり方
被害を抑えるだけでなく、住民が「クマがいても暮らせる」「安心して日常を営める」状態をつくることが次のフェーズです。つまり、被害抑制から「共存」への視点も加わるべきです。前知事が「山菜取り・子どもの遊び場・散歩」が奪われていると語ったように、暮らしの質を守る観点が重要です。
例えば:
- 子どもの遊び場・高齢者の散歩道の安全見守り体制。
- 地域観光・果実収穫・林業など、“暮らしと自然”をつなぐ産業を守るためのクマ対策。
- 教育・住民啓発を通して「クマは怖いだけでなく、どう対応すればいいか」を常識化する。
このように、住民ひとりひとりが “もう戦争だよ” と感じずに済む暮らしを取り戻すことが、長期的な課題です。
まとめ
「もう戦争だよ クマ 被害・東北の暮らし」という言葉には、数字では伝えきれない“恐怖”“切迫”“暮らしの喪失”が詰まっています。前知事佐竹氏の発言は、まさにその現実を端的に表したものです。
整理すると:
- 秋田県・東北ではクマ出没・人身被害・生活圏侵入が顕著に増加しており、住民の日常が脅かされつつあります。
- なぜ増えているかには、生態・環境・人口・暮らしの構造変化など複数要因が絡んでいます。
- 発言を契機に、自治体・住民・制度がクマ対策を再考し始めていますが、被害を“戦場化”と感じさせないためには、個人も地域も“備えと共生”の視点が必要です。
- 最終的には、クマと“距離をおく”だけではなく、「共に暮らせる」暮らしをどう設計するかが問われています。
住んでいる地域、通勤・通学路、山菜採り・畑のある方、子ども・高齢者がいる方――誰にとっても“クマの近くに暮らす”という現実は他人事ではありません。ぜひ、今日から「自分の暮らしでもできること」を考えてみてください。知ること、備えること、そして伝えること──その積み重ねが、「戦争だよ」という言葉をリアルな恐怖から少しずつ遠ざける道になるはずです。

とにかく、今年は異常。おそらく、冬眠に入らないクマも出てくるだろうなぁ~。
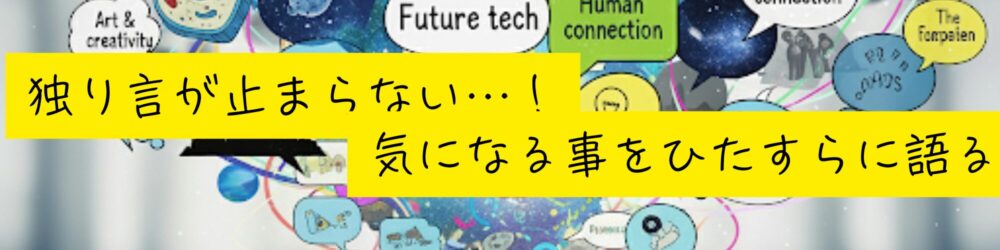
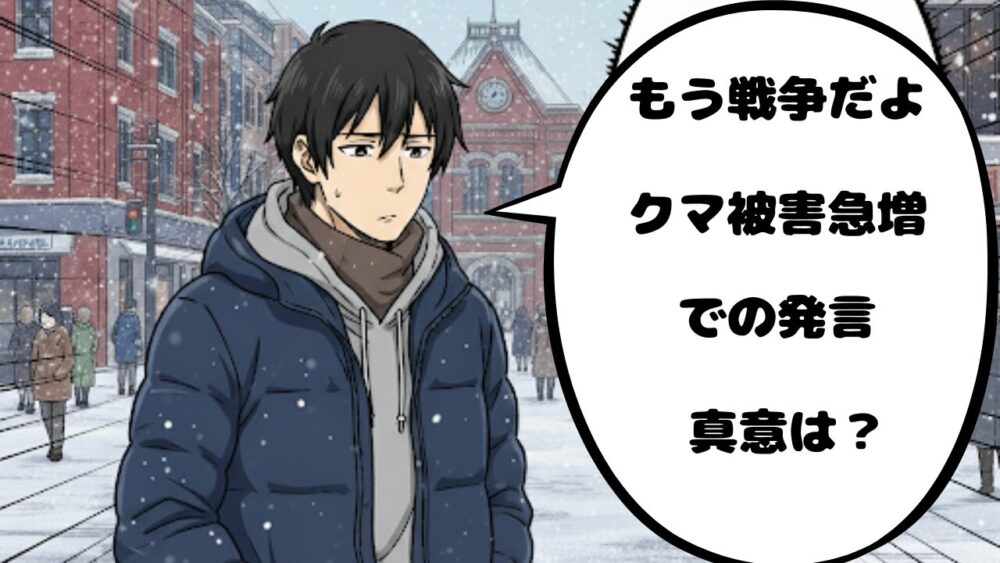


コメント