職場で同僚や上司から「○○ちゃん」と呼ばれたとき、なんとなく「嬉しい」と思う反面、どこかで「え、なんか気持ち悪い?」と感じる女性も少なくありません。
「私だけ?」「何でこう呼ぶんだろう?」とモヤモヤしながらネットで「ちゃん付け 職場 気持ち悪い 女性」と検索してこのページにたどり着いたあなた。安心してください。実は、その “違和感” はただの“敏感すぎる”というわけではなく、ちゃんと理由があります。
今回は、
- なぜ「ちゃん付け 職場 気持ち悪い女性」という感覚が出るのか、
- “ちゃん付け”される女性が抱える心理とは何か、
- その違和感が単なる個人的なものではなく、ビジネスマナーやジェンダーの観点でも考えるべきものだということ、
- 実際にどうすればその呼び方・距離感を自分にとって安心できるものに変えていけるか、
をじっくり掘り下げます。
「違和感だけど言い出せない」「でも気になる…」というあなたに、共感と少しのヒントをお届けします。

先に書いた、「ちゃん付け やめて ハラスメント裁判が話題に!呼び方が訴訟になる時代」について、女性の心理を深掘りしたいと思います。
なぜ「ちゃん付け 職場 気持ち悪い女性」という感覚が出るのか
“ちゃん付け”が生む距離感のズレ
まず前提として、職場という“仕事をする場”では、一般的に「○○さん」「○○部長」「○○課長」といった呼び方が多く用いられています。マナーガイドでも「下の名前で呼ばず、苗字に『さん』を付けて呼ぶ」のが基本と紹介されています。
それに対して「ちゃん付け」という呼び方は、親しみを込めたカジュアルなニュアンスを含むものです。“友人・後輩・プライベート感”がある呼び方とも言えます。
だからこそ、「職場というビジネスの場なのに“○○ちゃん”って呼ばれると、ちょっと距離がおかしくない?」と感じてしまう人が出てくるわけです。
特に、女性が“ちゃん付け”されると、「子ども扱いされた」「軽く見られてる?」という印象に繋がりやすいのです。
呼び方とジェンダー・役割意識の結びつき
さらに掘ると、この「ちゃん付け」が“ただのニックネーム”で終わらないケースがあります。呼び方が「性別」「年齢」「役職」「立場」といった属性と結びついており、特に女性に対して使われると「女性だから“ちゃん”」「年下だから“ちゃん”」という無意識の区別・軽視につながる場合もあります。
近年、こうした言葉遣いや呼び方が「ジェンダーハラスメント(ジェンハラ)」の観点で注目されています。例えば、女性だけを「○○ちゃん」と呼び、男性を名字+「さん」で呼ぶといった使い分けが、人間関係や評価に影響を及ぼすという指摘もあります。
この点から、「ちゃん付け 職場 気持ち悪い女性」という検索意図の裏には、呼び方の構造的なズレに気づいている女性の声があるのです。
職場マナー・呼称ルールとのギャップ
また、呼び方のマナー・ビジネスルールの観点から見ても、「ちゃん付け」が通例から外れていることがあります。実際、ある調査では「職場での呼び方」が「苗字」が74 %、「あだ名」が16 %という結果も出ています。
つまり、「あだ名・ニックネーム(ちゃん付け含む)」の呼び方自体が少数派であり、一般的な慣例ではないということです。
この慣例と実態のズレが、「自分だけ“ちゃん付け”されてて居心地悪い」という違和感を強めてしまうのです。
“ちゃん付け”で呼ばれる女性が抱える心理
ここからは、「私が“ちゃん付け”される立場だったらどう感じるか」という心理面を掘ってみましょう。実際に“ちゃん付け”されている女性が感じがちなこと、無意識レベルで抱えているかもしれない気持ちを整理します。
① 自分だけ“ちゃん付け”されているというモヤモヤ
「なんで私だけ“○○ちゃん”なの? 他の人は“○○さん”なのに…」という思い。
同僚や先輩後輩、上司・部下の呼ばれ方をふと見たとき、自分だけ特別扱い(?)されているように感じると、ちょっと居心地が悪くなることがあります。
「軽く見られてるのかな」「仕事では真面目に見てほしいのに、子ども扱いされた?」という気持ちが出てきても不思議ではありません。
② 親しみと侮りの境界線
「○○ちゃん」と呼ばれることが必ずしも悪いわけではありません。むしろ、フレンドリーな職場・若いチーム・カジュアルな会社では“ちゃん付け”が馴染んでいることもあります。
しかし、親しみとして受け止められるか、侮りや軽視として受け止められるかは、呼び手との立場関係・上下関係・社内文化・女性という属性などによって変わります。
たとえば、先輩や上司が部下・後輩を「○○ちゃん」と呼ぶのが、親しみ・励ましとして機能していればポジティブな印象になり得ます。一方、「私だけ“ちゃん”」という扱いだったり、呼び方のあとに「でも仕事は雑に扱われる」などの実感があると、「軽んじられてる」という受け取り方になりかねません。
③ 自分の尊重感・プロフェッショナル感への影響
仕事をしていれば、「私はこの役割で、こういう貢献をしている」「評価もされている」という実感が欲しいものです。しかし、“ちゃん付け”という呼び方が、無意識に「後輩ポジション」「遊び・雑談的な関係」「幼く扱われる」イメージを含んでいると、自分が“プロフェッショナルとして見られていない”という気持ちにつながることもあります。
つまり、「呼び方が軽い=仕事の中での扱いも軽い?」という連想に至ってしまっても、おかしくありません。特に女性で、職場での評価・立場・尊重を気にしている人にとって、この一点が“気持ち悪さ”“違和感”の根底にあることが多いのです。
④ “ちゃん付け”される女性の心理的反応パターン
具体的な心理反応を少し整理すると、こんなパターンが見られます。
- 「気にしすぎ?」という自分への疑問 →「私だけ気にしてるのかな…」「みんなフレンドリーだから私も気にしない方がいい?」
- 「言いたいけど言えない」葛藤 →「上司だし、言ったら雰囲気悪くなるかな…」「他の人は何とも思ってないのかも」
- 「我慢してるけどモヤモヤ蓄積」 →毎回「ちゃん」で呼ばれるたびに、少しずつ“軽く見られてる”という感覚が積もる
- 仕事・人間関係・メンタルへの影響 →「この呼び方が苦手だから、その人と関わる時気が重い」「無意識に避けてしまう」「評価されてない気がしてきた」
このように、呼び方一つでも、心理的な波紋は侮れません。
呼び方の“構造”として知っておきたいこと:マナー・ジェンダー・構造的視点
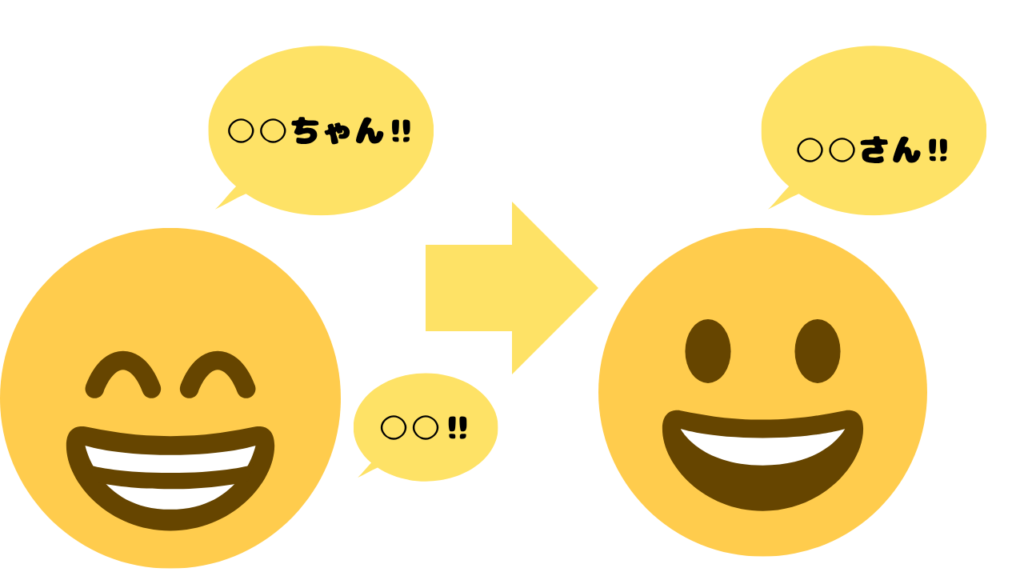
職場呼称のマナー的基準
「下の名前で呼ばない」「苗字に『さん』を付けて呼ぶ」のがビジネス呼称の基本という記述があります。
また、職場での呼び方に関するアンケートでは、ニックネームや“ちゃん付け”・呼び捨てが「あり」31%、「なし」25%、「関係性によってはあり」44%という結果も出ています。
これらから、「ちゃん付け」が決して主流・スタンダードではない呼び方であるということが見えてきます。
呼び方=距離感・立場・感情を示すコミュニケーションツール
呼び方というのは、ただの言葉ではなく「その人との距離」「敬意の有無」「立場」「関係性」などを内包しています。
「○○さん」「○○部長」と呼ばれるのは、仕事上の敬意・役職・役割を認める言い方です。一方、「○○ちゃん」と呼ばれると、どうしても「役割よりも人として」「子どもっぽい」「後輩・仲間感覚」といった印象がついてしまう可能性があります。
そして、この距離感・立場・感情のズレが、女性が「気持ち悪い」「違和感ある」と感じる根本的な理由になっていることが多いのです。
ジェンダー・役割固定観念との結びつき
ここがポイントです。単に呼び方がカジュアルなだけなら、それほど大きな問題にはならないかもしれません。しかし、女性だけが“ちゃん付け”され、男性は「さん」や名字+役職名で呼ばれているという構図があると、それは性別による扱いの差、役割意識の固定、軽視のサインとして捉えられます。
実際、「女性を“ちゃん”と呼ぶ」「女性には親しみやすさを求めて“ちゃん”付けする」という文化・クセが、ハラスメント(特にジェンダーハラスメント)に当たる可能性があるという観点も指摘されています。
この視点から、「ちゃん付け 職場 気持ち悪い女性」というキーワードで検索する人は、単に呼び方が嫌だというレベルではなく、「この扱われ方って私の立場・価値・評価に関わってるんじゃないか」という深い違和感を持っているということが読み取れます。
では、どうすれば「ちゃん付け 職場 気持ち悪い」という状況を変えていけるか
ここからは、「感じてしまう違和感を放置せず、少しでも自分にとって安心できる呼び方・距離感に変えていくための実践的ステップ」をご紹介します。
自分の“モヤモヤ”を言語化して整理する
まずは、呼ばれたときに「どう感じたか」を整理してみましょう。
- 呼ばれた瞬間、どんな気持ちになったか?(例:「幼く扱われた」「私だけ雑に扱われた」など)
- その呼び方が続いたとき、どんな気持ちになったか?(例:「なんとなく居心地が悪い」「仕事中もリラックスモードになってしまう」など)
- なぜその呼び方が気になるのか?(年齢・役職・性別・呼び手との関係など)
このように自分の感情や思考を整理することで、「なぜ“気持ち悪い”と感じるのか」がクリアになり、対処の方向も見えてきます。
無難な「敬称+名字/役職名」への誘導法
実際に、「○○さん」や「役職名+名字」で呼んでほしい」と伝えるのはハードルが高いかもしれません。でも、無言で変える方法もあります。例えば:
- 自分のメール署名・チャットネームを「○○(名字)さん」に設定する。
- 名刺交換・自己紹介時に「○○(名字)です。○○さんで呼んでいただけると嬉しいです」と“さん”を自ら使う。
- 会議時・チャット時に、他の女性 → “○○さん”で呼ばれているのを意識的に観察して、自分もその流れに乗る。
こうした “自分からトーンをセットする”ことで、呼ぶ側・呼ばれる側双方に「さん/役職呼びが普通」という空気を少しずつ作ることができます。
軽く「呼び方を変えてほしい」と伝えられる状況づくり
もし気になるなら、上司あるいは呼び手に軽く伝えてみるのも手です。ポイントは:
- 攻撃的にならない表現:「○○ちゃんという呼び方をしていただくのは嬉しいのですが、業務中には“さん”で呼んでいただけると集中できます」など。
- 自分の感情に焦点を当てる:「○○ちゃんだと、どうしても“若手”扱いされてる気がして…」というように。
- 選択肢提示:「もし良ければ“○○さん”で呼んでいただけるとありがたいです」など。
言い出しにくいなら、人事・総務窓口に「職場の呼び方で少し居心地悪さを感じてます」と相談するのも有効です。
職場風土・制度として変える意識も持つ
個人レベルの対応だけでなく、職場の制度や風土を変える意識も大切です。例えば、社内研修で「呼び方にも配慮を」と言われることも増えています。
呼称や言葉遣いがハラスメント防止・働きやすさの観点からも重要視されているという報告もあります。例えば、職場文化を見直す機会として「呼び方ルールを確認しよう」という社内アクションを取る企業もあります。
その意味で、自分が「呼ばれ方でどう感じているか」「この会社の呼び方文化はどうか」を観察しておくことは、働きやすさ・キャリア継続の面でもプラスになります。
よくある質問(Q&A形式で)
Q1. “ちゃん付け”=必ずハラスメント?
いいえ、必ずとは言えません。ただし、呼び方が性別・役職・年齢など属性と結びついていて、一部の人だけ“ちゃん付け”されているという構図があれば、ハラスメント(特にジェンダーハラスメント)の可能性が出てきます。
ハラスメントかどうかを判断するポイントとしては「意に反しているか」「継続的か」「職場環境に影響が出ているか」などがあります。
Q2. 自分だけ“ちゃん付け”されて気になるけど、言えずに我慢してる。どうしたら?
まずは自分の違和感・モヤモヤを整理することが大切です。そして、メール署名や自己紹介を「○○(名字)さん」で設定して、自ら“さん呼び”のトーンを作るのが手軽な第一歩です。言いづらいなら、信頼できる同僚や人事に軽く相談するのもアリです。
Q3. 呼び方が変わらないけど、仕事に影響ありますか?
はい、影響し得ます。「呼び方=距離感・立場・敬意」を含むため、違和感を感じ続けると「この職場では自分が評価されていないのでは」「軽視されてるのでは」という気持ちが募り、モチベーションやメンタルに影響が出ることもあります。
まとめ:違和感は敏感じゃない、むしろ大切な“信号”です
「ちゃん付け 職場 気持ち悪い女性」というキーワードで検索しているあなた。
その“気持ち悪い”という感覚、実はあなた自身が仕事の場・人間関係の場で“ふさわしい距離”を求めている証です。
以下、改めて押さえておきましょう。
- 職場では「敬称+名字/役職名」が基本であるというマナーと、「ちゃん付け」で呼ばれる実態とのギャップが、違和感を生んでいます。
- 呼び方は単なる言葉ではなく、距離感・立場・敬意・役割を内包しており、女性が“ちゃん付け”される場合、ジェンダー的な扱いや役割固定観念が背景にあることも少なくありません。
- 自分が「ちゃん付けされる側」で感じる違和感は、軽視されているかもしれないというサイン。無視しないことが大切です。
- 自分の気持ちを整理し、メール署名や呼び方の働きかけ、軽く直接伝えるなどのアクションを起こすことで、職場での呼び方・立ち位置・安心感を少しずつ変えることができます。
- 呼び方だけではハラスメントとは断定できませんが、「性別/役職/年齢などの属性との不均衡」「呼び方による不快感・仕事への影響」がある場合は、職場としても対応が必要なポイントです。
あなたが「ちゃん」とではなく「さん」で呼ばれ、尊重される職場に居続けられるよう、少しずつでも変化を起こしていきましょう。
あなたの感覚は、決して“敏感すぎる”わけではありません。むしろ、大切な信号です。

日頃から、気を付けないと・・・。
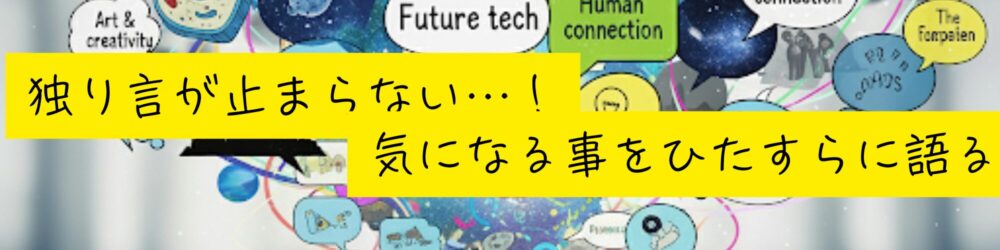
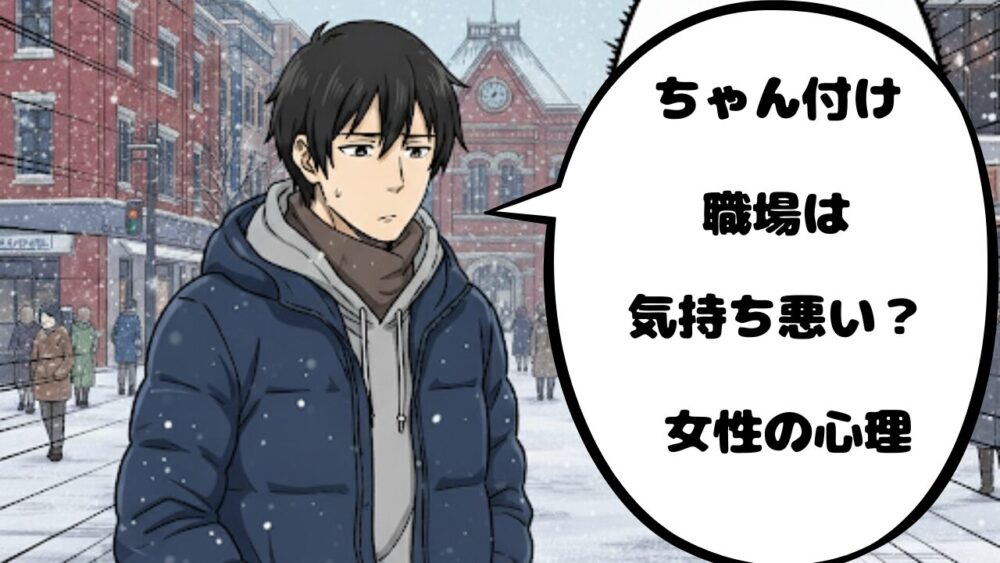


コメント