サポート終了後、安心では済まない未来
「Windows10 のサポートが終わる」──この言葉を目にして、「まあ、OS は起動するんだから大丈夫でしょ」と思う人もいるかもしれません。しかし、それは大きな誤解です。サポート終了後は、既知の脆弱性が放置される状態になり、新しい攻撃手法が日々生まれる中で、防御壁を失うリスクが急激に高まります。
これまでにも、サポート終了済みの OS を狙った大規模攻撃(例:WannaCry)があります。現実問題として、Windows10 を “無対応で使い続ける” 選択肢には、単なる “ちょっとの危険” では済まないトラブルの種が数多く潜んでいます。
この記事では、
- なぜ無対応運用が危険なのか
- 過去・最近起きた事例
- 将来的に起こりうるトラブルの具体像
- 安全性を確保しながら使い続ける/移行するための対策
を、できるだけ分かりやすく、かつ実践的にまとめます。
なぜ無対応運用が“火種”になるのか:脆弱性放置の恐怖

既知脆弱性とゼロデイ攻撃:防壁を失った OS は“餌食”
OS やソフトウェアの脆弱性(セキュリティホール)は、発見された時点で公表され、パッチ(修正)が出されます。サポート中はそれを適用して守ります。しかし、サポート終了後は 新たに発見された脆弱性についてパッチが出ない 状態が続きます。
- たとえば CLFS(Common Log File System) ドライバに起因するゼロデイ脆弱性「CVE-2025-29824」が 2025年4月に報告され、Microsoft はパッチ提供を行いました。これは OS のカーネルレベルで動く脆弱性で、特権昇格を可能にします。もしこのような脆弱性が発見された後にパッチが出ない OS を使っていれば、重大なリスクとなります。
- また、印刷スプーラーの脆弱性「PrintNightmare」は、Windows7 や 10 でも影響を受けるもので、過去に深刻な攻撃を引き起こした実績があります。
こうした “既知の脆弱性” は、攻撃者にとって格好の標的になります。なぜなら、同じ脆弱性は無数の端末に共通しているからです。
加えて、ゼロデイ攻撃(未公表・未修正の脆弱性を狙う攻撃)は、対応策が出る前に使われます。サポート終了後の OS は、これらを受け止める “盾” を持たない状態になりかねません。
過去事例:無対応 OS を標的にした大規模攻撃
WannaCry と EternalBlue(2017年)
これは最も有名な事例の一つです。Microsoft が Windows XP/Windows 7 など古い OS 向けのサポートを終了していた頃、SMB プロトコルに存在する脆弱性「EternalBlue」を悪用したランサムウェア「WannaCry」が世界中を猛威に震わせました。パッチ未適用の古い Windows マシンが次々と暗号化被害を受けました。
この攻撃を受け、Microsoft はサポート終了済みの OS にも緊急パッチを出す異例の措置をとりました。つまり、それだけ被害が甚大だったためです。

これ、覚えてます。システム部から、わんさか連絡がきて、すぐに対応した記憶があります。
サーバー OS におけるサポート切れ運用(Windows Server 2008 など)
企業のサーバー環境では、“サポート切れ OS を使いつづける” 例が過去にも多く確認されており、公開インターネットからのスキャンに晒されているものも多々あります。Rapid7 による調査では、サポート終了済みのサーバーが多数稼働しており、脆弱性を放置している実態が浮かび上がりました。
こうした実例を見ると、サポート終了済み OS をそのまま使い続けることが“現実問題としての危険”であることがよくわかります。
無対応 Windows10 を使い続けると起きうる将来トラブル
実際に起こりうるリスクを段階的に見ていきましょう。
1. セキュリティ侵害・マルウェア感染・ランサムウェア
すでに述べたように、攻撃者は既知脆弱性を探してスキャンし、無防備な端末を次々とマルウェアに感染させます。ユーザーデータの暗号化、システム乗っ取り、バックドア設置などが典型的な被害です。
特に ランサムウェア は近年の主流手法であり、企業・個人問わず被害額が膨大化しています。無対応の OS は防御が甘いため、攻撃を許す可能性が高くなります。
2. 権限昇格・制御奪取
通常のユーザーアカウントでログインしていたとしても、脆弱性を突くことで 特権昇格(admin 権限取得)が可能になることがあります。上述の CLFS 脆弱性がその典型例です。権限を奪われれば、システム全体を掌握され、意図せぬ挙動やデータ流出、システム改変が起こる可能性があります。
3. 情報漏洩・顧客データ流出・信用失墜
企業や店舗で使っている Windows10 が無対応状態であれば、個人情報、顧客情報、取引データなどが漏洩する可能性も増します。一度でも漏洩事故が起きれば、賠償・信頼回復コストは桁違いです。
また、個人でも、メールアカウント、ネットバンキング、クラウドサービス連携、オンラインストレージなどの情報が危険に晒されかねません。
4. 法律・規制・コンプライアンス違反リスク
企業や事業者では、個人情報保護法、各種セキュリティ基準、CSIRT 要件、業界ガイドラインなどが存在します。これらには「最新のセキュリティ更新を適用していること」などの要件が含まれていることが多く、サポート終了後の無対応運用は規定違反となる可能性があります。
万が一その状態で情報漏洩が発生すれば、「セキュリティに対して適切な努力をしていたか」の点で問われることになります。
5. ソフトウェア・ドライバの非対応・互換性破綻
OS が更新されないと、将来的にアプリケーションやドライバ、周辺機器ベンダー側が対応を打ち切る可能性が高くなります。
- 新しいアプリ・アップデート版が Windows10 非対応になる
- プリンタ、スキャナ、特殊機器のドライバ供給が止まる
- セキュリティソフト、ブラウザ、通信ソフトなども更新を打ち切る可能性
- OS の古さゆえに動作不良・不具合が出ても修正されない
こうなると、「使いたくても使えない」「動かない」ツールが徐々に増えていくことになります。

何の前触れもなく、動かなくなること多々あります。
6. インフラやネットワーク型攻撃(ボットネット化・DDoS 加害端末化)
ハッカーは無対応 OS をボットネットの“踏み台”にすることがあります。つまり、あなたの PC が加害者として使われ、他者へ攻撃を仕掛ける役割を強制的に果たす可能性があります。そうなると、自分のマシンが “加害側” の一部になってしまう怖さがあります。
また、企業ネットワーク内で無対応端末が侵入経路となり、組織内の他システムを侵食していく危険もあります。
7. 予期せぬシステム障害・クラッシュ・不安定化
OS が古く、周辺ソフトとの整合性が崩れていくと、予期せぬクラッシュや不安定化、システム破損が増える可能性があります。修復手段が提供されないため、トラブル復旧に手間とコストがかかります。
最近の警鐘・報道:無対応への現実的懸念

- Microsoft はサポート終了を前に、Windows10 利用者に対し「アップデート停止後、オンライン脅威に対する保護がなくなる」と警告を発しています。
- さらに、世界規模で約 4 億台以上の Windows PC が影響を受る“危機”が指摘されているとの報道もあります。
- 英国の消費者団体 Which? による調査では、サポート終了後にも使い続けようとするユーザーが多く、サイバー攻撃リスクを警告しています。
- また、SharePoint の旧バージョンを狙った攻撃例では、サポート終了間際・終了後の旧環境を標的にしてデータ侵害が発生しています。
これらは、ただ「理論上のリスク」ではなく、すでに現実として起きている問題です。
どうするか:リスクを最小化しながら使い続ける/移行する道
無対応で使い続ける選択をする場合でも、完全放任は最悪のシナリオを招きます。以下のような対策を組み合わせて運用することが不可欠です。
非常時対応策と防護策
- セキュリティソフト+アンチマルウェアを常備し、リアルタイム更新できる製品を選ぶ
OS の更新が止まっても、ウイルス定義ファイルなどは更新し続けるソフトを使う - ファイアウォール強化・アクセス制御
不要な外部アクセスを遮断、ルーター/ネットワーク側で制限 - ネットワーク分離やアクセス制限
重要なシステムやデータ処理部分をインターネット非接続領域に置く - バックアップ体制の強化
定期的・迅速なバックアップ、災害時に復旧できる構成を確保 - 最小限主義運用
使うアプリやサービスを絞り込み、攻撃対象を減らす - ログ監視・異常検知
システムログや通信ログをモニタリングし、不正挙動を早期発見 - 権限管理の徹底
日常操作は最低権限ユーザーで行い、特権操作は制限 - 仮想化隔離/サンドボックス運用
インターネットアクセスが必要な処理は仮想マシン上に隔離
延命策(たとえば ESU)を利用できるなら利用する
前述の拡張セキュリティ更新(ESU)は、延命手段の本命です。無対応運用に比べて安全性を大きく底上げできます。ただし、ESU はあくまで「猶予措置」であり、万能ではありません。
移行を視野に入れながら段階的に動く
最終的な理想形は、新しい OS やプラットフォームへの移行です。無対応を続けるなら、以下のような“段階的移行戦略”を持つべきです。
- まずは 移行可能性チェック:あなたの PC が Windows11 に対応するか(TPM2.0、CPU、セキュアブートなど)
- ソフト互換性・周辺機器対応の調査:使用中のソフトや機器が新 OS に対応しているかを確認
- 仮移行テスト:別ドライブや仮想環境で Windows11 や代替 OS を試してみる
- 移行タイミングを区切る:無期限に延命を続けるのではなく、期日を決めて移行
- 二重運用フェーズ:旧 OS と新 OS を併用する期間を設けてリスクヘッジ
最後に:無対応 Windows10 を選ぶのは“リスクの先送り”
この先、Windows10 を無対応で使い続けることは、“危険を先送りする選択”とほぼ同義です。
過去事例に学べば、無対応 OS が放置されておくと、マルウェア/ランサムウェア被害、情報漏洩、権限奪取、ネットワーク侵入、システム障害、規制リスクといった数々の問題が現実として発生します。
しかし、選択肢として無対応運用を採るなら、できるだけ防衛壁を強化し、移行のための猶予策を用意しつつ、必ず期限を切って切り替えるという戦略を取るべきです。

XPや7の時のようなことが、繰り返されないように祈るばかりです。
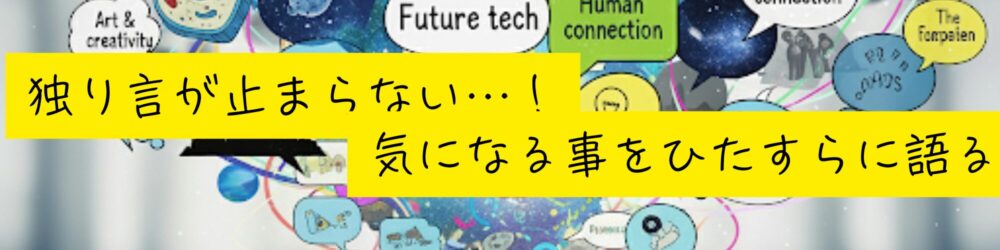
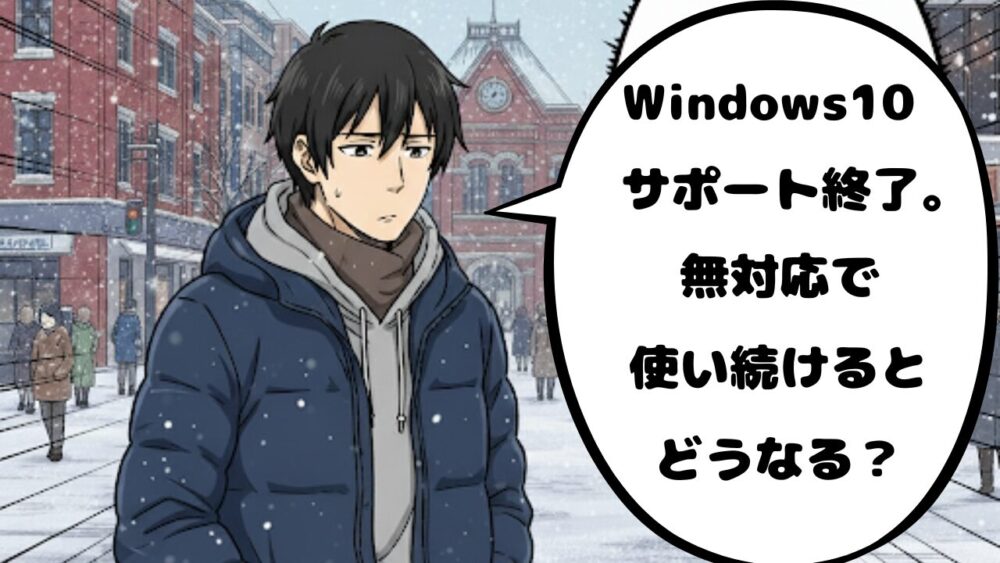


コメント