SNSで何気なく投稿した“つぶやき”──もはやそれが、著作権で守られる可能性がある時代に入ろうとしています。
2025年10月9日、東京地裁は、あるユーザーのツイートおよびアカウント画像をスクリーンショットで無断転載された件について、「著作物性」を認め、被告に約40万円の賠償を命じた判決を出しました。
この判決は、SNS発信・引用・転載文化にとって大きな節目になる可能性を含んでおり、「これからどうなるか?」を知りたい人は多いでしょう。
本記事では、以下の構成でわかりやすく解説します:
- なぜツイートが著作物認定されたのか? 判決と背景
- リポスト(リツイート・再投稿)はどうなる? 法的リスクと判断枠組み
- 今後どうなる? SNS運用・制度・AIとの関係性
- 実務的な安全運用チェックリスト
- まとめ:変化に備えるための心得
では、さっそく見ていきましょう。
なぜツイートが著作物認定されたのか? 判決と背景
判決のあらまし:無断転載に賠償命令
2025年10月9日、東京地裁は、原告が自身のアカウント画像と、特定の俳優応援ツイートをスクリーンショットされ、インターネット掲示板などに無断転載されたとして提訴した訴訟で、投稿を「著作物」と認定し、被告に約40万円の支払いを命じました。原告は約200万円を請求していたものの、裁判所は実情を踏まえて減額判断をしました。
杉浦正樹裁判長は、アカウント画像や投稿について「個性が表れたものといえ、思想や感情を創作的に表現したもの」にあたると認定し、著作権法上の保護対象としました。
この判決のポイントは、短文投稿・SNS投稿にも著作物性を認めうるという判断を明示したことにあります。
著作物性、創作性とは何か?
著作権法では、「思想又は感情を創作的に表現したもの」を著作物と定義しています。
この「創作的表現」がどこから認められるかが、著作物性判断の鍵となります。
投稿のような短文・断片的表現で創作性を認めるには、以下のような要素が裁判所で着目されることがあります:
- 表現における語り口・言葉選びなどの個性
- 感情・主張・語感のこもり方
- 表現の構成・改行・言葉遊びなどの工夫
- 単なる事実列記でない点
今回の判決では、アカウント画像との組み合わせや表現の個性を重視した判断がなされたようです。
ただし、著作物性の判断はケースバイケースであり、すべてのツイートが自動的に著作物になるわけではありません。
スクショ転載 vs 引用:違いと重要性
この判決で違法とされた行為は、スクリーンショットを撮り、それを外部サイトに転載・掲示する行為です。
“スクショ無断転載”は、引用の要件を満たさないケースとして判断されたわけです。
一方、法令で想定される「引用」の要件(著作権法32条)には、以下のようなものがあります:
- 引用目的が確立している
- 引用部分が主従関係上、従である
- 引用の必然性がある
- 引用部分の量が正当な範囲内
- 引用部分を明瞭に区別表示する
- 出所明示(投稿者名・日時やSNS名)
スクショ転載がこの基準を満たさず、かつ批評・引用という性格が弱い場合、違法とされるリスクが高まります。
過去にも、Twitterスクショ引用を巡る裁判例があり、違法と判断されたものもあります。
とはいえ、引用として認められうる可能性もあり、単なるスクショ=即違法とは言えません。
リポスト(リツイート・再投稿)はどうなる?:判断論点とリスク
ツイート著作物認定時代には、リポスト(リツイート/再投稿)も注目すべき論点となります。SNS上では自然な行為でもあるため、法的位置づけを理解しておくことが重要です。
リポストに関わる主な法理と過去判例
リポストを巡る議論で関係する法理には、主に次があります:
- 複製権、公衆送信権などの著作権利用権
- 著作者人格権(氏名表示権・同一性保持権)
- 引用の要件・例外規定
- プラットフォーム利用規約との整合性
もっとも有名な判例として、最高裁が扱った「リツイート事件」があります。この最高裁判決では、リツイート自体を著作権侵害と判断せず、ただしリツイート時に著作者名が消える、または表示されない仕様部分において氏名表示権侵害を認める判断が示されました。
この判例によれば、リツイート操作そのものが法律上の複製・送信行為と同視されるわけではないものの、表示仕様が著作者人格権を侵害する可能性は残るという理解が成立しています。
したがって、リポスト=全面的にリスクなし、というわけではなく、仕様によっては責任が問われるケースもあります。
リポスト=著作権侵害になるか? ケース別整理
以下は考えられる代表的ケースと法的評価の見通しです:
| ケース | 著作権侵害リスク | 人格権侵害リスク | メモ・判断要因 |
|---|---|---|---|
| 元投稿が著作物性あり、リポスト(公式RT機能) | 通常、著作権侵害とは判断されにくい | リポスト仕様で著作者名が消えると氏名表示権侵害の可能性あり | 元投稿者が投稿者本人である場合、黙示許諾と扱われやすい見解も一定程度存在 |
| リポストにコメントを付与して引用的利用 | 条件次第で合法性が高まる | 人格権リスクは低減 | コメントを付けて主従関係を明確にできれば安全性が上がる |
| リポストをスクショ化して再投稿 | 高いリスクあり | 複数権利侵害の可能性あり | スクショが著作物性を持つ可能性を含むため、無断転載扱いされやすい |
既存判例・解説では、リポストは「引用機能を使う/コメント付きでリポストする」という形式が最も安全性が高いと評価されることが多いです。
2025年時点でリポストはどう変わるか? 展望と注意点
ツイート著作物認定時代を迎えつつある中で、リポストに関しても次のような変化・注意点が出てくる可能性があります:
- 人格権保護の強化方向
リポスト仕様で著作者名が表示されない・切られる場合、同一性保持権や氏名表示権侵害を認める判例が今後拡大する可能性があります。 - プラットフォーム仕様改定・表示強制
SNSプラットフォーム側で、リポスト時に著作者名を必ず表示させる仕様を導入する可能性があります。また、リポスト許諾条件やクレジット表示ルールが利用規約で明記される可能性もあります。 - 判例の基準明確化
ツイート著作物性を巡る訴訟が増えれば、リポストの責任範囲・判断基準も積み重ねられ、より予見可能な法理が固まるかもしれません。 - 引用重視・代替手法への移行
単なるリポスト・スクショ転載ではなく、コメント付き引用・リンク・埋め込み表示を中心にする運用が主流になる可能性があります。
今後どうなる? 影響予測と注意すべき動き
このツイート著作物認定判決をきっかけに、SNS文化・制度・デジタル表現全体にわたる変化が想定されます。
SNS運用・メディアへのインパクト
- 引用・転載運用の見直し必須
スクショ転載や全文転載はリスクが高まり、引用方式・埋め込み方式へのシフトが求められます。 - まとめサイト・転載サイトの動揺
ツイート丸写し・スクショ転載が中心だったまとめ文化に再検討の機運が出るでしょう。 - 企業アカウントでの注意強化
他人投稿引用・転載・リポストの運用ルールを見直し、法務チェック体制を整える必要性が高まります。 - 発信者(クリエイター/一般ユーザー)側の意識変化
投稿内容や表現にオリジナリティを意識し、権利表示や許諾の枠組みを意識した発信が増えていくでしょう。
制度・法改正・AIとの関連
- 著作権法改正の余地
デジタル投稿・SNS表現を念頭においた著作権法の例外規定拡充、裁定制度などの制度整備が議論される可能性があります。 - AIと著作権の絡み
投稿が著作物とみなされるなら、AIモデルの学習素材利用・生成物との類似性問題において、ツイートコンテンツも引き合いに出されることになるでしょう。 - 国際ルール・プラットフォーム規約の整合化
SNSプラットフォームは各国法令対応を進め、利用規約を更新・強化する可能性があります。ユーザーは常に仕様・規約の変更をチェックしておく必要があります。
実践!著作物認定時代の安全運用チェックリスト
以下は、SNS担当者・メディア運営者・一般発信者がリスクを抑えて運用するための実践的ガイドです。
発信者として気をつけるポイント
- オリジナル性を意識し、他者表現を過度に参照しない
- 投稿記録を保存(スクリーンショット、ログ、タイムスタンプ)
- 権利表示・クレジット表記をつける習慣
- 利用許諾表明(プロフィールや利用条件に許可範囲を明記)
引用・転載時の安全性チェック
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 引用目的 | 批評・紹介・解説といった目的があるか |
| 主従関係 | 自分の文が主、引用部分が従か |
| 必然性 | 引用がないと伝えにくくなる理由があるか |
| 引用量 | 全体に対して過度になっていないか |
| 区別表示 | 引用部分が明瞭に区別されているか |
| 出所明示 | 投稿者名・日時・SNS名を明記しているか |
- 埋め込み機能を使う(プラットフォーム公式の埋め込み方式)
- スクショ転載を安易に使わない
- 許可取得できるなら事前に投稿者から承諾を得る
リポスト(リツイート/再投稿)時の留意点
- 公式リツイート/引用リツイート機能を使う
- コメント付きリポストで主従関係を明示
- リポスト仕様によっては著作者名が消えるケースもあるため、著作者名表示が自動付与される設定や機能に注目
- リポストをスクショ化して再投稿するのは、転載行為とみなされやすいので避ける
組織・メディア運用体制の強化
- 運用ガイドラインを明文化(引用・転載・リポストルール)
- 投稿前チェックフロー設置(法務・権利確認)
- 削除・異議申立て対応フロー構築
- 担当者向け研修・教育実施
トラブル時の初動対応
- 指摘があればまず削除
- 謝罪・誠意ある対応
- 必要ならば専門家・弁護士に相談
- 裁判化を避ける方向を常に念頭に置く
まとめ:リポストも含めて「安全運用」が求められる時代へ
- 2025年10月の東京地裁判決で、SNS投稿(ツイート・アカウント画像)が著作物として認定され、スクショ無断転載に対して賠償命令が下されたという事実は、SNS文化の転換点になる可能性を持ちます。
- 単なる引用・転載・リポストといった行為であっても、時と場合によっては著作権侵害や人格権侵害と見なされるリスクがあります。
- 特にリポスト(リツイート・再投稿)は、仕様・コメント添付・表示形式などによって判断が変わる領域です。
- 今後、著作権法改正・AI生成文脈・プラットフォーム仕様改訂など、制度・技術環境が変わる可能性が高いため、運用者・発信者ともアンテナを高くしておく必要があります。
- 安全運用をするためには、引用ルールを守る、スクショ・全文転載を避ける、許諾を取る、表示形式を意識する、組織的なチェック体制を構築する、という対策が現実的かつ重要です。

衝撃のニュースだったので、取り急ぎ作ってみました。
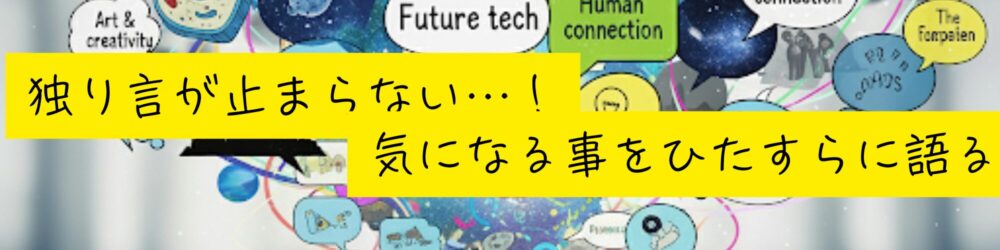
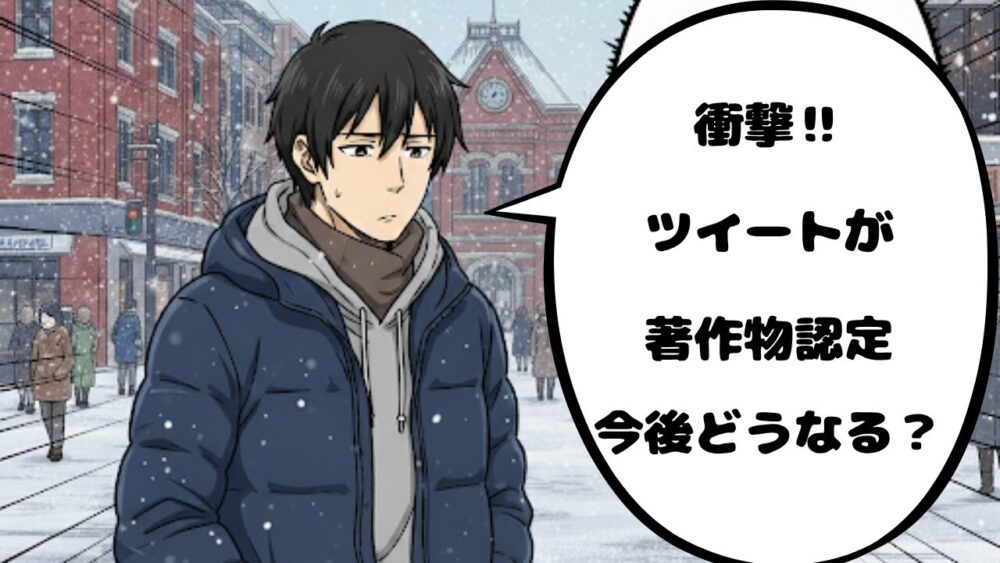


コメント